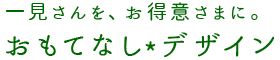人生初めてのお茶事は、平成最後の初釜でしだった、おもてなしデザイナーの洞澤葉子です。
一見さんをお得意さまにするブログを見ていただき、ありがとうございます。
平成最後の初釜が終わってから、10日ほどたち、今年初めてのお稽古に。
茶道を始めて、もうすぐ一年になろうとしていますので、昨日のお稽古は、心なしか先生が厳しかったような・・・。
でも、それも「上達の証」と捉えれば、嬉しいものです。
茶道は、お茶を飲むだけじゃない
お茶には、濃茶と薄茶があります。
お店で飲めるような、一般的な抹茶は、薄茶です。
濃茶は、その名の通り、もっと濃くてどろっとしたものを、数人で分け合っていただきます。
濃茶を飲んだあとに、道具の拝見という問答があります。
亭主(お茶を点ててくれる人)が、その一杯のために用意してくださった、道具たちを見せていただきます。
茶入れの形や窯元、茶入れを入れる袋のこと、そして茶入れから茶碗にお茶を入れるときに使う、スプーン状の茶杓というものがあります。
それぞれについて、お客様から尋ねられて亭主が答える、という段取りを踏みます。

この問答の時が、実は亭主の力量を推し量る時間でもあるようです。
用意した道具たちが、どのような人の手で作られて、どのような歴史を経て、どのような曰くつきで、その場にいるのかを披露するのですから、茶道に関してはもちろん、焼き物や布地、歴史などの深い教養が必要になります。
そして、この拝見の時間にお客様は、亭主がどれだけ自分のために、心をこめて席を用意してくれたのかを、推し量ります。
センスを磨くためには
お稽古の問答中に、季節の言葉を言う場面がありますが、昨日そこで「寒椿です」と答えた私に、先生は「直球過ぎて、無粋ね~」と言われました。
自由に言葉を選んでいい場面なので、結構センスが問われる瞬間でもあります。
デザインの仕事をしてきたので、「粋」とか「センス」という意味の言葉には反応してしまいます。
よく「センスがないから・・・」といわれる方がいらっしゃいますが、美的センスについては、後天的なものだと思っているので、誰でもセンスを磨くことができます。
「センス」とは、どれだけ良いものを見てきたか、どれだけ知識を持っているか、どれだけ善し悪しの判断ができるか、この3点で決まります。
つまり、たくさん良いものを見たり聞いたりして、それについて調べて、その知識を元に善し悪しが判断できるようになれば、センスがあると言われるようになります。
あなたも、何かセンスが問われる瞬間には、この3つを思い出してみてください。
私も季節の言葉に磨きをかけるべく、今日は精進する日にします(笑)
メルマガ購読
そのために抑えるべきポイント、また、その根底にあるべき、お客様のことを本気で考える「おもてなし」の気持ち。
そんな、お客様に「思い出してもらう」ために必要な要素を、毎日メールでお届けします。