
こんにちは。
茶道教室に通い始めて一年、いまだに「お茶杓のご銘は」と聞かれてしどろもどろの、おもてなしデザイナー洞澤葉子です。
なぜ40歳を過ぎて茶道教室に通うようになったのかといえば、決して花嫁修業ではございません(笑)
着物が好きで、日本文化に興味があって、四季をしみじみ感じられる齢になり、もっと知りたい感じたい!と思ったことがきっかけでした。
そこで、あれこれ探して見つけたのが、着物、書道、華道、礼儀作法、建築などの総合芸術である「茶道」でした。
学んでみると、この茶道の考え方が、実はビジネスと深いつながりがあると感じたので、ここにまとめてみることにしました。
利休七則
日本の「おもてなし文化」に大きな影響を与えたといわれる、千利休の教えに「利休七則」といものがあります。お茶の基本の心構えである「おもてなし」について、利休が遺した七つの心得です。
この「おもてなし」の心得は、インターネットやAIが普及し、人と人とのコミュニケーションがさらに重要視されていくこれからの時代のビジネスに、大きく通じる部分があると感じたので、ご紹介します。
利休七則
- 茶は服のよきように点て
- 炭は湯の沸くように置き
- 花は野にあるように生け
- 夏は涼しく冬暖かに
- 刻限は早めに
- 降らずとも傘の用意
- 相客に心せよ

1.茶は服のよきように点て
「抹茶は飲む人にとって、ちょうど良くなるように点てましょう」という意味です。
自分の理想のお茶を追求するのではなく、相手のことを考えて、時には少しお茶を冷ましたり、お菓子を食べる速さに合わせたりするなど、気配りが必要ということです。
自分のスキルや専門性をアピールするばかりでなく、受け手が「何を求めているか」をよく考えて、伝え方を変えていくなどすると、ビジネスの現場で生かせそうですね。
デザインの現場ではよく言われることですが、デザイナーはアーティストではないので、自分がカッコいいと思うものを作るのではなく、お客様が成果を出すために効果的なものを作りましょう、ということです。
2. 炭は湯の沸くように置き
「炭はお湯が沸くように置きましょう」という意味ですが、炭に火をつけさえすれば必ずお湯が沸くとは限りません。
炭の準備はお客さまから見えないことも多いですが、ここを怠ると火がうまくおきません。
言葉だけ聞くと当たり前のことのようですが、裏方での準備を怠ると大切なところがうまくいかない、という教訓です。
ホームページやLP、チラシなどの集客ツールを、頑張って作りこんだとしても、そこからメールアドレス登録なのか問合せなのか、興味を持ってくださったお客様が次に何をしたらいいのか、あなたのところまで来てくださる道筋をきちんと用意してあげないと、上手くいかないということですね。
3. 花は野にあるように生け
茶室には花を飾りますが、その花の生け方は「自然にあるように生ける」のが基本なのだそう。
これは、野原の風景をそのまま切り取るという意味ではなく、剰余を取り除いた少ない要素で野原を想起させましょうという、本質を追求する姿勢を言っています。
仕事をする上でも、商品・サービスの本質は何かを追求し、過剰な装飾をそぎ落とすことで、その魅力がさらに際立つということなんです。
パレートの法則(2:8の法則)で言われるように、「仕事の成果の8割は、費やした時間全体の2割の時間で生み出している」ので、その重要な2割は何なのかを追及していきましょうということです。
長くなりましたので、続きは次の記事で。
メルマガ購読
そのために抑えるべきポイント、また、その根底にあるべき、お客様のことを本気で考える「おもてなし」の気持ち。
そんな、お客様に「思い出してもらう」ために必要な要素を、毎日メールでお届けします。
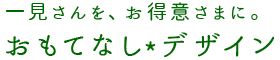

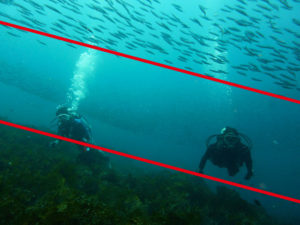

“利休七則から見る、おもてなしのビジネス” に対して1件のコメントがあります。