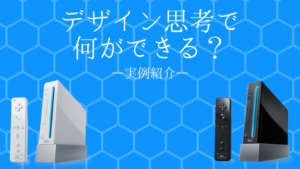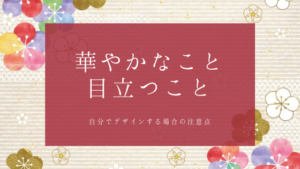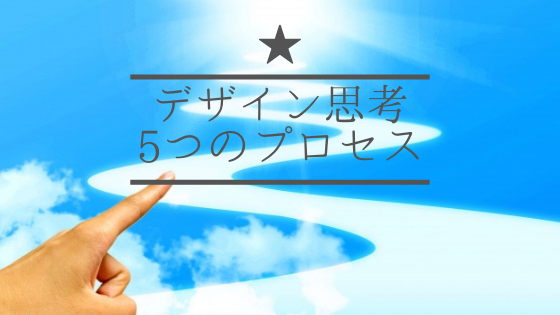
こんにちは。
一生懸命伝えようとすると、つい話が長くなり、「その話あと何分?」と言われて、ムキーッとなる、おもてなしデザイナーのほらさわ葉子です。
お客様にモノを届けるには
さて、以前の記事で、お客様にモノを届けるためには、5つのポイントがあることを書きました。
忘れてしまった方は、こちらをどうぞ(笑)
この5つのポイントは、デザイン思考の5つのプロセスでもあります。
デザイン思考の5つのプロセス
1. 観察/共感(誰にボールを投げるのか)
まずは、あなたのお客様をよく観察し、お客様のことを理解します。ここで重要なのは「常にお客様視点であること」。
お客様の目線で考えることで、課題やその背景が見えてきます。
例:どうすればDVDドライブよりも薄いノートブックパソコンを作ることが出来るだろうか?そもそもDVDドライブは必要なのか?
2. 問題定義(どんなボールが欲しいのか)
お客様をよく観察することで、「お客様が困っていること」「なぜ困っているのか」が明確になります。
この段階では、さらに掘り下げた観察と問題定義を繰り返しながら、真の問題はどこにあるのかを、見つけ出しましょう。
場合によっては、「そもそも観察対象が違うのでは?」といった、根本的な軌道修正を求められる場合もあります。
例:出来るだけ軽くて薄いパソコンを作り出すため、DVDドライブ以外にも通常のHDDやLANジャックも取ってしまおう。いまどき、多くのユーザーはWifiとクラウドを利用するのが主流だからだ。
3. アイデア創出(どんなボールを作るか)
どんなアイデアがお客様に受け入れられるか、思いつく限りのアイデアを出してみましょう。現実にできるかどうかは加味せず、とにかく出してみることが重要です。
たくさん出したアイデアを、決定および検証する際には、仮説をより具体的にすることが大切です。
- 悪い例:○○○という情報があると、申込みが増える
- 良い例:メインビジュアルの下に○○○という情報があると、お客様が登録に進む、心理的ハードルが下がる
例:パソコンの最終スペックには出来るだけ”攻めた”アイディアを盛り込み、周りの人々の反応を確かめてみる。今までに無いタイプのものを作るので、見た目も最新的なものにする。
4. プロトタイピング(どんな形、色にするか、どう投げるか)
プロトタイピングとは、試作化するということです。
お客様の視点に立ち、抱えている問題を発見し、解決方法のアイデアを出したら、検証するためにプロトタイプ(試作品)を作りましょう。
形のある商品の場合は、模型を作ってみる。
WEBサービスの場合は、画面のイメージを並べてみる。
リアルな体験の場合は、四コマ漫画のようにストーリーボードにしてみる。
こうして作ることによって、口では伝えきれないアイデアを再現できたり、次のようなチェックがしやすくなります。
- そのアイデアは、物理的・技術的に実現可能か?
- UI(ユーザーインターフェイス)/UX(ユーザーエクスペリエンス)としてどうか?使いやすくなっている?
プロトタイプを作る時に便利な、簡単に作図ができるサービスもありますので、活用してみるのもいいですね。
例:出来るだけ薄くて軽量なノートブックパソコンを作り出す為に、光学ドライブとLANジャックを廃止し、USBも2つのみ、そしてフラッシュドライブ記録デバイスとして採用する。そしてデザインは出来るだけスタイリッシュに。
5. 検証(ボールを拾ってもらえるのか)
プロトタイプ(試作品)ができたら終わりではありません。
ここからお客様に向けて、検証・改善を繰り返し、試行錯誤しながら、より良い商品・サービスにしていきます。
その時注意しなければならないのが、検証してもらう相手が、ターゲットとなるお客様なのかという点です。ターゲットをしっかりと絞り込んでおかないと、関係のないフィードバックに右往左往する羽目にもなります。
もう一つ、ゴールをしっかり設定しておきましょう。お客様のどんな問題を解決したらゴールなのかを決めておかないと、いつまでも終わらない、修正の無限ループに陥ります。
例:今までのプロセスで決定した事柄を元に実行、できました!

最後に、もう一度「デザイン思考」を振り返ってみます。
「デザイン思考」とは、デザインに必要な考え方と手法を利用して、ビジネス上の問題を解決する方法。
デザイン思考はデザイナーだけの考え方ではなく、ビジネスに携わる全ての人に関係する考え方です。
商品・サービスを作る以外にも、プロジェクト進行や、組織課題を考える時など、あらゆる場面でデザイン思考が活用できます。デザイン思考を活用して、あなたのビジネスがもっと発展していったら、嬉しいです。