
子供が3人いるので、授業参観は大忙し、おもてなしデザイナーの洞澤葉子です。
一見さんをお得意さまに変えるブログを見ていただき、ありがとうございます。
先日、授業参観があり、次男(小4)の教室へ行ったとき。
授業は「道徳」でした。
その時に先生が「君たちはもうすぐ5年生。高学年の仲間入りです。これまでたくさんのことを学んできて、良いことと悪いことの区別ができるはすです。低学年の見本となるよう、正しい行動をしましょう。」というようなことを言いました。
私はこれに少し違和感を感じました。
正しさの基準は人それぞれ
先生のおっしゃっていることは、至極まっとうな事で、年下の子達の模範となるような態度をとりましょうという意味は、理解できます。
でも、善悪の判断や正しさは、絶対的な基準というものはなく、住んでいる土地や時代によって、または個々の経験や考え方によって、変化するものなのではないでしょうか。
例えば、不倫は悪とする文化もあれば、一夫多妻の文化もある。
牛乳は身体にいいという人たちもいれば、良くないという人もいる。
もし「年下の子には優しく」という正しさを持っている人が、我が家の次男(小4)が三男(小1)を泣かせているのを見たら、どんな状況でも次男を批判するでしょう。
でも、本当にそれが正しいの?
三男が、次男の大切なものを壊したかもしれない、悪口を言っているのかもしれない、先に手を出したのかもしれない。
正しさの基準は人それぞれ。
正しさばかりを追っていると、本当に大切なものを見失う危険性があります。
だから、正しさを振りかざして、他人を批判するのは怖いなと思うのです。

自分の当たり前は、人の当たり前ではない
ビジネスをしていくときに、「いや、それ、絶対違うでしょ!」と感じる場面は、少なくないと思います。
そこでお互いに正しさを押し付けあっていけば、何も生まれてきません。
時に相手を傷つけることにもなります。
自分の当たり前は、人の当たり前ではない。
このことを忘れずに、自分の正しさをちょっと脇に置いて、相手の正しさに耳を傾けることで、お互いの正しさの中にある妥協点を見出して、生産性を高めることができます。
大切なのは、絶対的な正しさの追求ではなくて、同じゴールに向かって協力して進んでいくことです。
感情に任せて善悪を判断したり、犯人探しをすることではなく、今の状況に対してどんな最善策があるのかを考えることに、時間を費やすほうが、効果的ではないでしょうか。
今日はぜひ、正しさを振り風していないか、自分の行動を振り返ってみましょう!



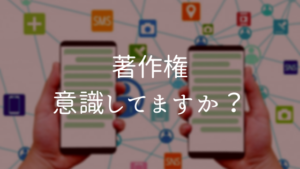
“正しさのぶつかり合いは、何も産み出さない” に対して1件のコメントがあります。